�@�@���@�\������
�@�@���@�s���r
�@�@���@�J�Êփ��J�s����
�@�i�Q�l�j
�@�@�@�O�@��t�����̒n�Ɉ�˂��@��A��ː�����������ƐԂ��Ȃ�܂����B
�@�@�@���n���u�Ԉ�v�̗R���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�y�فz�\�����Ԉ䉷��
�@�ؒʂ���i��ł���ƁA�E��ɕW���u�\�����Βn�v������܂��B
�@�W���u�\�����Βn�v
�@�@�@
�@
�u�\�����Βn�n�C�L���O�R�[�X�ē��@���l�s�ΐ��ǁ@H16.3�v
�@�@�@
�@�O�̕����ɓ����A�Ȃ��Ă��܂��B�����̓����s���܂����B
�@���̓��͋A��ɒʂ��Ă��܂����B
�@�@
�u�L��v
�@�\�����Վ�O�̍L��ł��B
�@�@�@
�@
�@�\�����́A�����N�ԁi1661�`1673�N�j�ɒn���̋v����a��L�V���A�ő��㎛�̎q�@�������Ɉڐ݂��ċ��������M�R�n���@�ł��B
�@�n���@�́A����2�i1869�j�N�����A�Ђɂ��Ď����܂����B
�@���\7�i1694�j�N�A�S�z�T�t���̋��̌i�F���Â�ŁA�������猩���������̏��i�������ɉr�̂��u���i�v�̂͂��߂ŁA
�@�̐�L�d�����̒n���ނɁu���B���i�v���A���`�������Ƃō]�ˌ���ɂ͏������V�R�ɖK���悤�ɂȂ�A
�@��ʂ̗v���ł��������\�����ׂ̗ɂ͒��X���݂���ꗧ�����n�Ƃ��đ�ϓ��킢�܂����B
�@���݂́A���a3(1803)�N�ɍ]�˂̏����S���\�l�ɂ���Č��Ă�ꂽ�u���i�����n�v�̐Δ肪�c���Ă��܂��B
�i�W���j
�@�u���l�s�n��j�Ձ@�\�����Ձv
�@�u���a�Z�\�O�N�\�ꌎ����o�^�@���l�s�v
�@�u������\�N�O���v
�@�@�@
�@
�����V���i�����n�聄
�@���a3(1803)�N�̌����ł��B
�@�@�@
�i�����j
�u�\������
�@���̏ꏊ�ɂ́A�������ߍ��܂Łu���M�R�n���@�v�Ƃ������@������A�\�����ƌĂ�Ă��܂����B
�@�u�\�����v�̖����o�Ă����ԌÂ������́A��������̕����\���N�i��l���Z�j�w�~�Ԗ�ᶑ��x�ŁA����Ɂu�Z�����v�̖����o�Ă���̂ŁA���̎���ɔ\�����������������킩��܂��B�Â��́A�Z�����A�̂����A�\�����ȂǂƂ��Ă�Ă��܂����B
�@�������A�n�܂肢���͕s���ŁA�]�ˎ���ɏ����ꂽ�w�\�������N�x�ł́A�������㓡���������������n�܂�Ƃ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��\�����̖����t�����̂��ƌ����ƁA�悭������i�\��������j����Ƃ��A���������Ƃ����G�t�����̌i�F��`�����Ƃ������A���܂�̔������ƒ��̖������̕ω��̂��ߕ`�����A�M���̂Ă̂�����������i�̂����j�Ƃ��A�n����{���Ƃ���Z���\���̈Ӗ�����ȂǁA���̑����낢��Ȑ�������܂��B
�@�\�����́A���ߏ����Ȓғ��ł����B�܂��A���ꂳ�����������オ����܂����B������]�ˎ���̊����N�ԂɂȂ��Ă��̒n��̒n�Ƃ����v����a��L�V���A�]�ˑ��㎛�̔p�@�ł������n���@�������Ɉڂ��čČ����A���@�Ƃ��Ă̔\�����̗��j���n�܂�܂��B
�@��ʂ̗v���ł��������\�����́A���]�����炵�������̂ŁA���̌i�F�𒆍��́u�n�Ô��i�v�ɓ��Ă͂߂āA�Â�����l�X�́A�u���i�v�Ă�ł��܂����B���̎����A�c���\��N�i��Z��l�j�ɏ����ꂽ�w���畨��x�Ƃ����{�ɏo�Ă��܂��B����ƍN�����̌i�F�������A�]�ˏ�̉��G�ɂ���������̌i�F���`����Ă��܂��B���̌�A�S�z�T�t���\�����ɗ��āu���i�v�̊������r���ŗL���ɂȂ��Ă����܂����B
�@�����̕��l�n�q���������̒n��K���悤�ɂȂ�A������I�s���⎍�A�̂ȂǂɎc���A�G�t�����͂�������̊G��`���܂����B�܂������ɔ�Ȃǂ����Ă��A�\��������͈ē��}�i�}�Q�j�Ȃǂ�����o����܂����B
�@�}1�́A�V�یܔN�i�ꔪ�O�l�j�ɏo�ł��ꂽ�w�]�˖����}��x�ɕ`���ꂽ�\�����̗l�q�ł����A�ɉh���Ă��������̎p��m�鎖���o���܂��B�{���͓�Ԕ��i�l�E�܂��j�l���ŁA�{���͒n���ł����B�傫�ȏ��́A���������̓`��������M�̂̏��ŁA���̎�O�ŁA�]��������i�F�����Ă���l�����܂��B
�@�\�����͖�����N�i�ꔪ�Z��j�ɉΎ��ɂȂ�A���̌�Z�E�����Ȃ��Ȃ�܂��B���̏�S���⑼�̓����o���������߁A���т�āA�K���l������ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�����č��́u���V���i�����n�v�̔�Ȃǂ��A�����̖ʉe�𗯂߂邾���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v
�@�@�@
�u�]�˖����}��@�\�������M���v
�@��������A�{��G�t��������������̓���]�̏��i��`�����Ƃ��܂������A
�@���܂�̐�i�ɊG��`���̂�f�O���A�G�M�����̖̍����ɓ����̂Ă��i�M�̏��j�Ƃ̓`��������܂��B
�@���́u�̕M���v�́A�吳9�i1920�j�N�̑啗�Ő܂�A����ɑ����m�푈�����̏���������邽�߂ɍ�������@��o����Ă��܂��܂����B
�@�@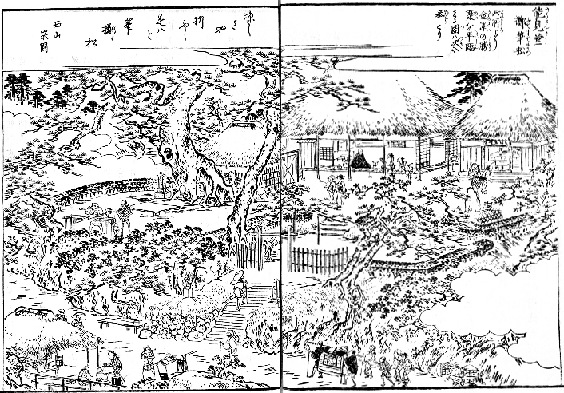
�u���C�����i�}��@�\�������̏������V���i���]�v�i�L�d�j
�@�\�����̕M�̏�����̒��]��`���Ă��܂��B
�@�L�d��u���i�v�̉�肪�W�J���L����Ă��܂��B
�@�@
�u���z���i��i�v�i�L�d�@�������������ّ��j
�@�\��������̒��]��`���Ă��܂��B�����ɖ쓇�������܂��B
�@�@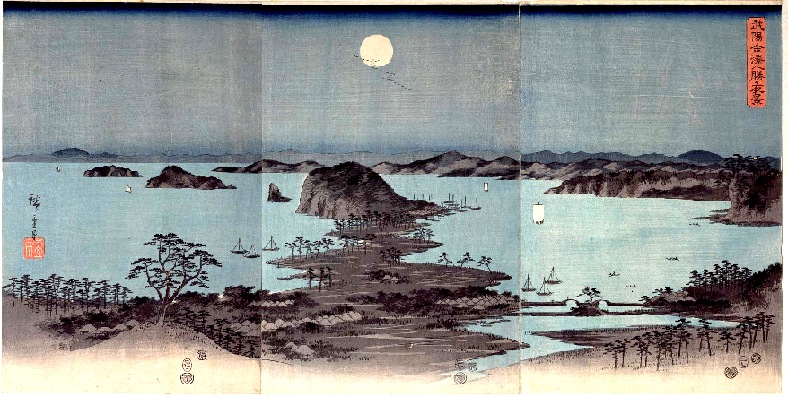
���\�����Ղ̐Δ聄
�@�@
�i�����j
�u������
�@�I���ĂȂ�Ö���̌�
�@�����N���A������������ɂ��Ă��ڍׂ͕s�������A�����҂̊�������g�́A���ۏ\��N�i�ꎵ�O�l�N�j�n�Ƃ̍]�˂̗L���ȏ���i�{�̏o�ŁA�̔����j�ł������B
�]�˘O���R���
�@�S���̏��̕ʂ��قƂƂ���
�@���R�͍]�ˋg���̗V�s�̎�l�B�o�~��n�ݐᒆ���ΎR�剺�B������N�i�ꔪ���j���q�ɂ�������R���A���̏����������A�����i����H�ׂ钎�j�̏Z�݉ƂɂȂ�Ȃ��悤�A���̈������\�����ɂ���߁A���̏�ɕs���̔�����Ă��Ɨ��ʂɍ��܂�Ă���B
���������V��
�@���i���N�i�ꎵ�����N�j�t�A����ɗV�����l�����A�\�����ɔ��܂�A
�����A�r��͂Ă����ɂ�K�ꂽ�B�l�̑��������͍̂r�p���邪�A���R�̔������͉i���ł���ƋC�Â����Ă��ꂽ�\��������̔������i�F�Ɋ��S���o���A���̔�����Ă��B
�@�����l���́A���b�ŁA�w�l��l���W�x�ɂ���Ė���m��ꂽ�B�v
�R���@�a���m���
�@�]�˂̈�җ�؏@�a�̕�ŁA���ĕM�̏��̍����ɂ������B
�@�\�����̌i�F���������@�a�́A�����ɐ��O�̋��ۏ\�Z�N�i�ꎵ�O��N�j�ɕ�����āA���̌㖾�a���N�i�ꎵ����N�j�ɖS���Ȃ��Ă���A��Ɏ����̉̂������A���̏ꏊ�ɑ���ꂽ�B
�@������Ԃ����݂����ނ����ɂā@���ӂ�������̖��͂��ނ��
���V���i�����n��
�@���a�O�N�i�ꔪ���O�j�����B��̖����́A�]�˂̏��Ɛ}��c���i���c�ؓ����Y�j�������A���ʂɂ͕S���\���̍]�˂̐l�����̖��O����L����Ă���B
�\�����Ղ̐Δ�ɂ���
�@�]�ˎ��ォ�獡���܂ŁA�\�����Ɏc����Ă�����́A�B����i�����n�肾���ł������B
�@������\��N�A��������ɔ\��������x���Ɉڂ��ꂵ���Δ�O�_�i�R���v�a���m���A������A���������V��j���n��̕������Ƃ��Ċ��p����邱�Ƃ��肤���L�҂̕���������Ɋ��ꕽ���\�Z�N�ɁA�쓇����\�����K�i���Ɉڂ��ꂽ���R�̋��ƂƂ��ɁA�\�����Ղɖ߂鎖�ƂȂ����B
�@�����̐Δ�͍]�˂̒m���l�������A���̏ꏊ�������Ɉ����Ă���������Ă���B
�@�@����N�㌎�@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v
�@�@
�u������v�u�]�˘O���R���i�\�j�v�u�]�˘O���R���i���j�v�u���������V��v
�@�@�@
�@
�@
�u���M�@�R���@�a���m�v���
�@�@�@
���ۈ�ꓰ�N�V�聄
�@�@�@
����˂̐Ձ�
�@�@�@
�@�\�����Ղ���K�i������āA�ē��E��̋}�ȊK�i������Ă����܂��B
�@����n��ƁA�s���r�ł��B
�@�@�@
�@ �J�Êփ��J�s�����e�ɂ���ꂽ�r�̂��ߕs���r�Ɩ��t�����܂����B
�@�@�@
�@�s�����́A���Ƃ��Ƃ͒J�Ð�̐����n�����A�����n�߂��ɂ���܂����B
�@���a62�i1987�j�N�̋��l�}�s������Ђɂ���n�J���Ō��݂̏ꏊ�Ɉڂ�܂����B
�@�@�@
�@
�@�Ȃ��J�Ð�͋��ɉw�̐��H�����ɗ�����ŁA�قƂ�ǂ͈Ë��ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@
�i�蕶�j
�u�J���L�O
����A�А��A���J�ˁA���R�A�ւ̒J�˂̉��[���J�����A�V���A�G�ؐ�����ΔZ���m�ɁA�\���i�̐ΊK�̒��A�А��l-��Ԓn�ɒJ�Êւ��J�s��������������Ă����B�n���͕s�ڂ����̂�葺�l�̐M�Ă��A���N�ꌎ��\�����ɏ��s���Ղ肪����ɍ����Ȃ������Ă���A�������̒J�Ԃ������Ɛ������N���o���A���݂��J�Ð�̐����n�ł���B���Ă͋��ɉw��т܂ł̐��c�ɟ��p���Ƃ���Ă����B�����ɂ́B�����B����ō։����������Ƃ̓`��������B��͊֓���k�Ђŕ����B�������ӂ͎l�G�܁X��X�̖쒹�̂������肪������A���Ăɂ͌u����т����A�H�ɂ���x���Q���сA����̂����炬�������ꂽ�B�ՐÂȑf���炵�����̒J�˂ł������B���܂��܋��l�}�s������Ђ̑�n�����ɂ�荟�̒n�ɑJ�������B
�@�@��@�ΐ�@���v
�@�@
���s�����^�萅���^�s������
�@�@�@
�@
�@�s��������A�s���r�쑤�̒ʘH���u�\�����Ձ@���Ɂv�i�݂܂��B
�@�@�@
�@�u�f4�v�y�сu�f3�v�n�_
�@���̐�ŁA�傫�����]���J���܂��B
�@�@�@
�@�\�����Ղ̓쑤�ɂ���u�x�e�L��v�ł��B
�@�������������ݒu����Ă��܂��B
�@�@�@
�@
�i�����j
�u���i�Ɣ\����
�@�̂̋���́A���C�����n�̉��܂œ��荞��ł���A�����\��������̒��߂͑f���炵�������i�����n�`�}�Q�Ɓj�B
�@�����ɂ͖[���̎R���݂���]�˘p�A�p�ɕ����ԓ��X�A�����p�A����ɂ͎O�Y�����̎R�X�A�����āA�����ɂ͗��E�x�m�܂ł���]�ł����̂ł���B
�@�������㏉���̋{��G�t�E���������������������̌i����`�����Ƃ������A���C�̊����Ŏ��X���X�ƕω������i�ɕM���i�܂��A���ɊG�M�����̍����ɓ����̂Ă��Ƃ̌����`���Ɉ��ށu�M�̏��v�̓`�����c���Ă���B
�@�]�ˎ���̌��\�̍��A�����o�g�̖S���m�E�S�z�T�t���̒n��K��A��������̕��i���n�Ô��i�Ɏ��Ă������Ƃ���A�u�����J�E���ˏH���E�F�萰���E������E��������E�쓇�[�ƁE��䃋A���E�̖��ӏ��v�Ƒ肵�����i�̊������r�B���ꂪ���݁A��X���m����i�Ƃ����Ă���B
�@���̍��̋���̒n�͊��q�E�]�m���ƈ�̂ƂȂ����ό��n�ł������B�����āA�̐�i�����j�L�d���͂��߂Ƃ��鑽���̊G�t�╶�l�n�q�ɂ��u�i���n�E���i�v���Љ��A�����̗��l�œ�������B�܂��A���̃n�C�L���O�R�[�X�̈ꕔ�́A�����A�ۓy���J�h�������ւ̎�v���i���j�ł������B
�@�}�P��1853�N�ɉ̐�L�d���`�������n����̒��]�}�ŁA�`���ꂽ���͍����牎���A�ē��A�G�X�q��A�쓇�B�����̋����A���ˋ��B�E���ɂ͕M�̏��A���ł���B
�@�}�Q��17���I�̒n�`�ɐl�̎肪�������Ȃ������̕����n�`�}�ŁA���͔\�����B
�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v
�@�@
�u��������̎ʐ^�B
�@���ɖ쓇�A�����ɐ��˂̓��C����F��E���ˋ����͂���ŕ����p���A�E�ɐ��ː_�Ђ̐X����]�ł���B���˂̓��C�͖��ߗ��Ă��Ă���i�D�T�V�c�Ȃǁj���A���i�ꗗ�̖ʉe���c���Ă���B
�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v
�@�@
�u��������̎ʐ^�B
�@����̕ۓy���J�����̂ڂ�ƁA�u�M�̏��v����ۍ��������B���̉��ɂ́u���i�����n�v�Δ肪������B
�@�E�̑�n�ɂ͐Γ��U�Ȃǂ��c��B
�@�@2009�N9���@���������@�\�����Ւn�����v���W�F�N�g�v
�@�@